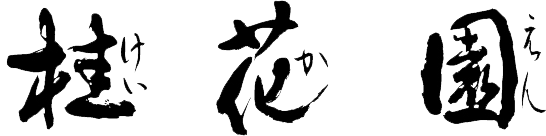当園のアジサイは五分咲きになりました。清流沿いのヤマアジサイとカシワバアジサイは満開です。
カシワバアジサイは、ピラミッド形に咲く白い花と柏の葉っぱのような大きな葉っぱが特徴で、この葉っぱは秋に紅葉しますので長期間楽しませてくれます。
カシワバアジサイは最近人気の「アナベル」と同じアメリカ原産のアジサイです。
管理は簡単で花後の剪定だけです。カシワバアジサイは一般的なアジサイ同様、夏以降にできた花芽が翌年に開花しますので7月までに剪定をお勧めします。剪定した花はドライフラワーで楽しめます。
ただ、たくさんの花をつけますので、特に雨を含むと自重で枝ごとたわむことがあります。支柱を立てて枝を結束すると見た目もきれいですが、花が咲き続けると花が横になったり下向きになったりする様子もカシワバアジサイだけが見せてくれる趣ですので、それも楽しましょう。
年: 2025年
サラサウツギが満開です。
当園のウツギの種類を数えてみました。ヒメウツギ、タニウツギ、ベニバナウツギ、ノリウツギ、ダルマウツギ、コガクウツギ、マルバウツギがあります。
その中でも、サラサウツギは小さな花が枝いっぱいに咲きますので一番見ごたえがあります。
「ウツギ」を漢字で書くと「空木」、名前の由来は枝が成長すると中心部が空洞になることによります。枝の中が空洞で大丈夫かと思われますが、あえて空洞にすることで枝全体の重量を抑えることができ、枝が細くても高く伸ばせることができます。竹と同じです。
ウツギはアジサイと同じで挿し木で簡単に増やすことができます。一株購入して挿し木で増やしてウツギエリアを作ると愛着のわくお庭ができますよ。
名前は、知らん
今日は二十四節気の「小満」、草木が茂り始める頃とされており、「小さく満ちる」とは、まだ満足な状態ではなく少しずつ成長を始める頃という意味です。
また、お百姓さんはこれから田畑の仕事も忙しくなり、「小さな満足」を得られる時期とも言えます。
植物にうとい人に、この花の名前を知っていますかと質問すると、「知りません」と答えが返ってきたら、オヤジギャグの出番です。
シラン(紫蘭)は洋風ガーデンでも和風庭園でも主役を引き立てる最適な宿根草です。
シランを地植えにすると、水やり肥料も不要で、こぼれ種からどんどん増えていきます。ズボラな人には最適な植物です。
ガンセキランが咲いています。
ゴールデンウィーク中はテレビで紹介されたことから多くのお客様に来園いただき、テレビの影響の大きさに驚くばかりでした。
今、ガンセキランが咲いています。
ガンセキランは茎の根本にバルブと言われる偽球茎が岩石に似ていることからこの名前が付けられました。
高知県にある牧野植物園でガンセキランの大群落を見ることができます。
葉っぱに班点模様がある種はホシケイランと呼ばれ、斑点模様のある植物はツワブキやアオキ等たくさんありますが、そのなかでもホシケイランの模様は一番きれいと思います。
キエビネの群生
キエビネは別名「オオエビネ」とも呼ばれています。キエビネやオオエビネの名前からも分かるように、ジエビネと比較すると花が黄色で株や花が大きいのが特徴です。葉っぱは雑木の間からの木洩れ日を集めるために大きくなったみたいです。
エビネは日陰の植物だと思われますが、うす暗い環境で育てると株はやせて花はほとんど付かず、明るい日陰を好んでいるみたいです。
当園のエビネ植栽地には一本のヤブツバキが自生しており全体的にうす暗い環境でした。これではエビネがかわいそうだと思いヤブツバキを伐採したところ、直射日光が当たるようになり、逆に一部の株が傷んでしまいました。覆水盆に返らず。
それでも今年もジエビネやキエビネたちはきれいな花を咲かせてくれました。
散策日和
今日は、暑くもなく寒くもなく雨もなく風もなく曇り空で最高の散策日和でした。
今当園は芝桜や黄桜が満開で、エビネラン・スズランやクルメツツジが咲きだしました。
今年は2月の寒波の影響で例年より2週間ほど開花が遅れています。
今日清流沿いを散策されたお客様から、素朴だけど素晴らしい空間だったと有難い言葉をいただきました。
シャガは増えすぎます。
シャガは学名、アイリスジャポニカと付いているほど、日本原産と思われますが、中国から渡ってきた帰化植物です。シャガの名前は射干(しゃかん)という中国読みからきていますが、射干はもともとヒオウギだったのですが、いつの間にかシャガになったみたいです。
シャガは3倍体植物ですので種はつくれません。人の手で生息地の範囲を広げていきます。ヒガンバナやヤブカンゾウと同じです。
シャガは常緑樹の下などで湿り気のある明るい日陰でよく育ちます。当園のシャガ数年前に桂造園の圃場から移植した数株のランナーがどんどん伸びて群生しました。
サツマイナモリ
サツマイナモリの名前の由来は、鹿児島の固有種というわけでなく、関東地方以南の南九州でよく見られ、イナモリソウに似ているからだそうです。
サツマイナモリ、今でいうと鹿児島イナモリ、鹿児島のイナモリといえば、令和4年に逝去された稲盛和夫さんを連想します。稲盛さんの功績は周知のとおりですが、中でも会社更生法を適用したJALをわずか3年で再上場させるという偉業を成し遂げたことは驚きであり、しかも無報酬だったそうです。
稲盛さんは多くの名言を残されており、その一つに「リーダーは常に謙虚でなければならない」という言葉が知られています。
サツマイナモリの一株ずつはそれぞれ謙虚な花を咲かせますが、群生すると圧倒的なパワーを見せつけます。
今、清流沿いの散策路でサツマイナモリの花が見られます。
春蘭が咲いています。
春蘭(しゅんらん)の名前は春に花を咲かせることに由来しています。
また、春蘭は名前のとおりラン科の植物で、ランは地中の菌からも養分を得ており、菌がなければうまく育ちません。
当園の椿山には春蘭がたくさん自生していますが、春蘭の数倍自生しているヤブ蘭に似ており、春蘭の花は薄い緑のために気がつかずに通り過ぎてしまします。春蘭の花を見つけたら、上から眺めるのでなく腰を落としてなるべく下から観察してみてください。質素ながらも高貴な花を見ることができます。
春蘭は別名「ジジババ」と言われ、花びらにある班点が老人の顔にあるシミに似ていることから名付けられたようです。
ホトケノザ
ホトケノザを漢字で書くと「仏の座」、葉っぱが円状で縁に切れ込みの様子が「仏様が座る台座」に似ていることから、ホトケノザと呼ばれるようになりました。また、葉っぱが3階建ての屋根に見えることから「サンガイクサ」(三階草)という別名もあります。
ホトケノザはシソ科に属しており、花はシソ科の特徴の鳥のくちばしに似た「シンケイカ」(唇形花)で、多くの花を咲かせますが、そのうちいくつかの花は開花することなく、つぼみの中で自家受粉して種を作っています。
種にはアリが大好きな物質があり、アリに種を遠くまで運んでもらっています。
ちなみに、春の七草のホトケノザは、「コオニタビラコ」のことで、ホトケノザは毒はありませんが食べられません。