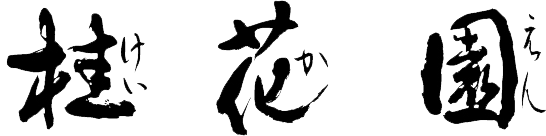春蘭(しゅんらん)の名前は春に花を咲かせることに由来しています。
また、春蘭は名前のとおりラン科の植物で、ランは地中の菌からも養分を得ており、菌がなければうまく育ちません。
当園の椿山には春蘭がたくさん自生していますが、春蘭の数倍自生しているヤブ蘭に似ており、春蘭の花は薄い緑のために気がつかずに通り過ぎてしまします。春蘭の花を見つけたら、上から眺めるのでなく腰を落としてなるべく下から観察してみてください。質素ながらも高貴な花を見ることができます。
春蘭は別名「ジジババ」と言われ、花びらにある班点が老人の顔にあるシミに似ていることから名付けられたようです。
月: 2025年3月
ホトケノザ
ホトケノザを漢字で書くと「仏の座」、葉っぱが円状で縁に切れ込みの様子が「仏様が座る台座」に似ていることから、ホトケノザと呼ばれるようになりました。また、葉っぱが3階建ての屋根に見えることから「サンガイクサ」(三階草)という別名もあります。
ホトケノザはシソ科に属しており、花はシソ科の特徴の鳥のくちばしに似た「シンケイカ」(唇形花)で、多くの花を咲かせますが、そのうちいくつかの花は開花することなく、つぼみの中で自家受粉して種を作っています。
種にはアリが大好きな物質があり、アリに種を遠くまで運んでもらっています。
ちなみに、春の七草のホトケノザは、「コオニタビラコ」のことで、ホトケノザは毒はありませんが食べられません。
寒緋桜と緋寒桜
染井吉野が咲きだす前に寒緋桜は、真っ赤と言うより濃いピンク色の花を下向きに咲かせます。
私は最近まで寒緋桜と緋寒桜の違いが分かりませんでした。どう見ても同じような花なのに場所によって、寒緋桜の名札があったり緋寒桜の名札があり不思議に思っていました。ググってみると、なんと寒緋桜と緋寒桜は同じ種類だと知りました。
緋寒桜(ヒカンザクラ)とは全く別種に彼岸桜(ヒガンザクラ)があり、「カ」と「ガ」を聞き間違えることから、緋寒桜より寒緋桜の方がより使われるようになったみたいです。
併せて緋色ってどんな色なのかググってみると、緋は「あけ」と読み、茜色は「やや暗い赤」で緋色は「鮮やかな赤」だそうです。
染井吉野が育たない奄美地方や沖縄県では、サクラと言えば寒緋桜が一般的です。
写真は桂造園本社前の満開の寒緋桜です。