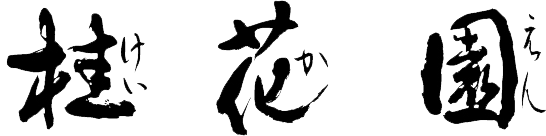キエビネは別名「オオエビネ」とも呼ばれています。キエビネやオオエビネの名前からも分かるように、ジエビネと比較すると花が黄色で株や花が大きいのが特徴です。葉っぱは雑木の間からの木洩れ日を集めるために大きくなったみたいです。
エビネは日陰の植物だと思われますが、うす暗い環境で育てると株はやせて花はほとんど付かず、明るい日陰を好んでいるみたいです。
当園のエビネ植栽地には一本のヤブツバキが自生しており全体的にうす暗い環境でした。これではエビネがかわいそうだと思いヤブツバキを伐採したところ、直射日光が当たるようになり、逆に一部の株が傷んでしまいました。覆水盆に返らず。
それでも今年もジエビネやキエビネたちはきれいな花を咲かせてくれました。
月: 2025年4月
散策日和
今日は、暑くもなく寒くもなく雨もなく風もなく曇り空で最高の散策日和でした。
今当園は芝桜や黄桜が満開で、エビネラン・スズランやクルメツツジが咲きだしました。
今年は2月の寒波の影響で例年より2週間ほど開花が遅れています。
今日清流沿いを散策されたお客様から、素朴だけど素晴らしい空間だったと有難い言葉をいただきました。
シャガは増えすぎます。
シャガは学名、アイリスジャポニカと付いているほど、日本原産と思われますが、中国から渡ってきた帰化植物です。シャガの名前は射干(しゃかん)という中国読みからきていますが、射干はもともとヒオウギだったのですが、いつの間にかシャガになったみたいです。
シャガは3倍体植物ですので種はつくれません。人の手で生息地の範囲を広げていきます。ヒガンバナやヤブカンゾウと同じです。
シャガは常緑樹の下などで湿り気のある明るい日陰でよく育ちます。当園のシャガ数年前に桂造園の圃場から移植した数株のランナーがどんどん伸びて群生しました。
サツマイナモリ
サツマイナモリの名前の由来は、鹿児島の固有種というわけでなく、関東地方以南の南九州でよく見られ、イナモリソウに似ているからだそうです。
サツマイナモリ、今でいうと鹿児島イナモリ、鹿児島のイナモリといえば、令和4年に逝去された稲盛和夫さんを連想します。稲盛さんの功績は周知のとおりですが、中でも会社更生法を適用したJALをわずか3年で再上場させるという偉業を成し遂げたことは驚きであり、しかも無報酬だったそうです。
稲盛さんは多くの名言を残されており、その一つに「リーダーは常に謙虚でなければならない」という言葉が知られています。
サツマイナモリの一株ずつはそれぞれ謙虚な花を咲かせますが、群生すると圧倒的なパワーを見せつけます。
今、清流沿いの散策路でサツマイナモリの花が見られます。