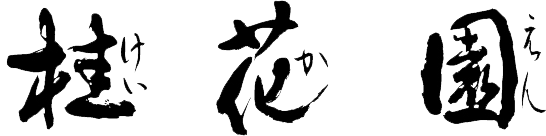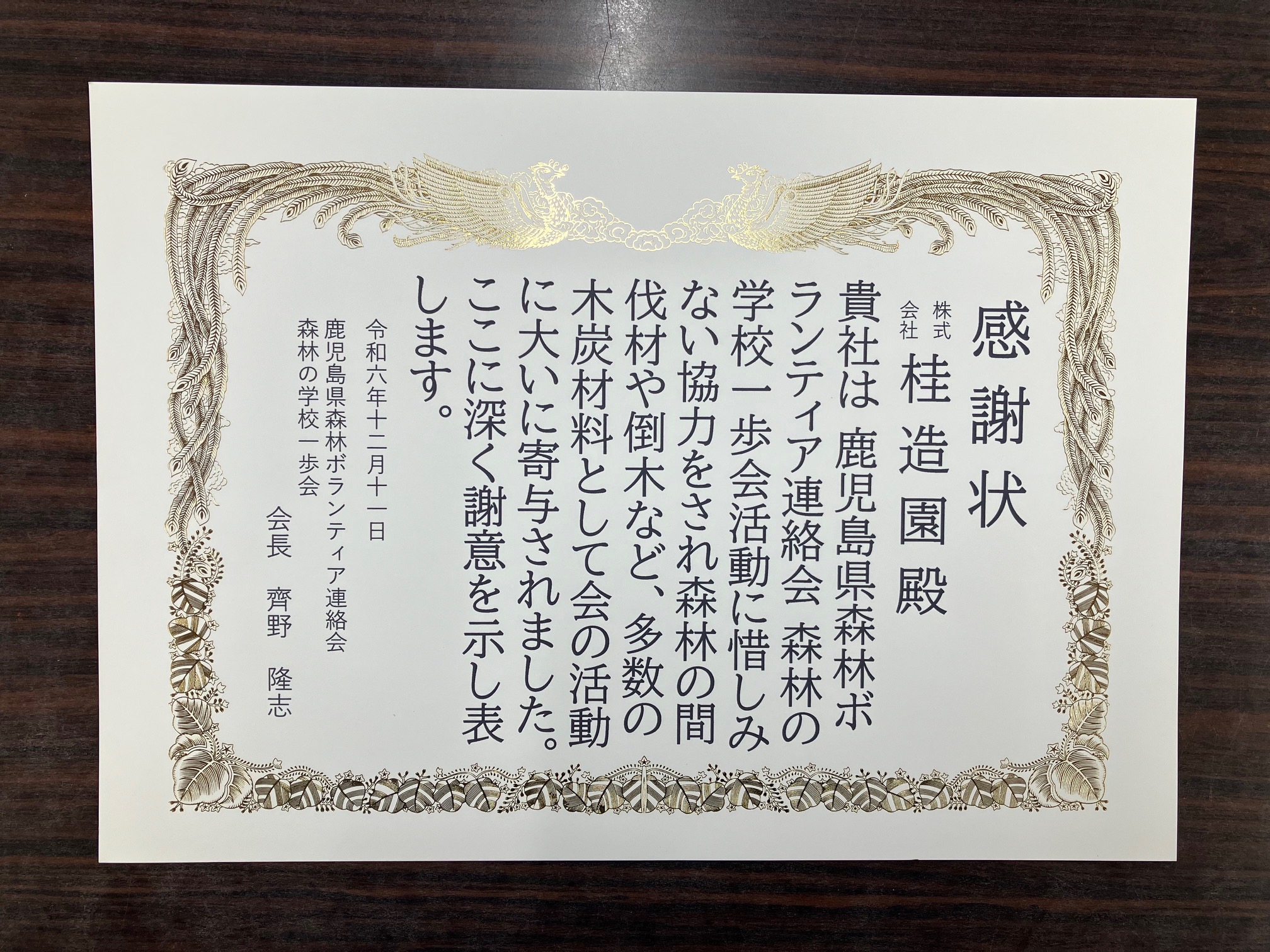桂花園及び桂造園は、長年にわたり炭焼きの原木や薪を寄贈していたことに、ボランティア団体から感謝状をいただきました。
ボランティア団体は会員の高齢化にともない、原木の調達が困難な状況とのことで、トラックで原木を届けると大変喜ばれます。
これからもSDGsの取り組みの一環として、できることをしていきます。
年: 2024年
さざんかの歌
12月になるとさすがに寒さを感じます。当園のモミジはまだ紅葉していませんが、さざんかは咲きだしました。
さざんか さざんか さいたみち
たきびだ たきびた おちばたき
あたろうか あたろうよ
しもやけ おててが もうかゆい
皆さんご存知の童謡「たきび」の歌詞です。
この歌のモデルになったさざんかの垣根は現存しています。
この歌は昭和16年にNHKこどもラジオ番組で放送されましたが、当時戦時中だったため、たき火は敵の攻撃ポイントになると想定されたことから、3日で放送中止になったそうです。
作詞者は幼児でもすぐ覚えられるように、すべてひらがなで発表しました。
愛しても 愛しても ああ ひとの妻
赤く咲いても 冬の花
咲いて さびしい さざんかの宿
昭和57年に大ヒットした大川栄策さんの「さざんかの宿」です。
言うまでもなく不倫の歌です。
さざんかが持つ寂しさが、「ひまわりの宿」とか「コスモスの宿」より、やはり「さざんかの宿」の方がイメージ的に合ったのでしょう。
幼児向けならOK、不倫の歌はNGとさざんかは思っているでしょう。
これから寒さが厳しくなりますので、指宿スカイラインの交通状況を鑑みて、暖かくなるまで冬季休園します。
知足のつくばい
椿山の入口につくばいがあります。つくばいとは茶室前に置かれる手水鉢(ちょうずばち 手を洗って身を清めるもの)のことです。
このつくばいの本物を知っている人もいらっしゃると思いますが、枯山水で有名な龍安寺にあり、水戸黄門様が寄進されたと言われています。
つくばいの水をためておく真ん中の四角い溝を口の字に見立てると、稲垣吾郎さんの吾、浅香唯ちゃんの唯、足ながおじさんの足、知識の知、になり、吾 唯 足 知(われ ただ たるを しる)と読みます。直訳すると、私は満ち足りていることだけ知っている、ということになり、満足することを知っている者は貧しくても幸せであり、満足することを知らないも者はたとえ金持ちでも不幸である、と禅では教えています。
物や情報に満ち溢れた時代にあっても、人はそれぞれ、衣食住、地位、名誉等のモノサシを心の中に持っていて、自分にとって必要なもの、必要なモノサシを知る、そしてそのモノサシの目盛りで満足することを知りなさい、と言うことでしょうか。
また、龍安寺の枯山水は大小15個の石を配置しただけの庭で、一見15個の石はバラバラに並べられているように見えますが、庭のどこの位置から眺めても、15個の石のうち必ず1個は他の石に隠れており、14個の石だけしか見えないように配置されています。この寺に置かれたつくばいは、15個全部の石を見ることができないことを不満に思わず、14個も石を見れることを満足とする心を持っている者は幸せと教えているみたいです。そしてもう一つの石が見れないことから、足らざるを知る、を悟っています。
たった4文字のつくばいですが奥が深いですね。某国の某大統領には「馬の耳に念仏」ですね。
ツヤツヤ葉っぱのツワブキ
ツワブキの花が見頃になりました。
ツワブキの葉っぱはフキに似ており、フキの葉っぱにツヤツヤの光沢があることから、ツヤハフキからツワブキになったらしいです。
このツヤツヤはクチクラ層で、葉っぱの表面から水分の蒸発や紫外線・乾燥だけでなく病原菌の侵入を防いでいます。
ツバキの葉っぱで知られているクチクラ層は、葉っぱの表面に光を反射することで光合成も助けています。
なお、葉っぱの表面がツヤツヤしている常緑広葉樹が多くみられる森林は照葉樹林(しょうようじゅりん)と言いますね。
「コケテラリウム」作り
本日、森林ボランティア団体主催の「コケテラリウム」作りイベントがありました。
「コケテラリウム」とは、ガラス容器の中にコケをメインに小さい森や風景を作るもので、お金もかからず手軽に作れることから最近人気があります。
ガラス容器に入れる植物の材料は現地採取で、コケや小さなモミジ等見つけてから始めました。
参加者は初めての体験で、ちよっぴり不安ながらもワイワイ言いながら作りあげた作品は、どれも個性的なテラリウムとなりました。
午後から園内を散策しました。シャクナゲ園のコケワールドエリアでは小さいコケテラリウムでは味わえないダイナミックな魅力を感じていただきました。
春に咲く花
10月に入り暑さも少し和らぎ始めました。我が家では春に咲く花を種から育ててみようと種を買ってきました。
草花の多くは春に花を咲かせます。理由は夏が苦手というより、原産地の違いにより高温、多雨、多湿等で夏期では生きていけないために、春に花を咲かせ種を作り、種や球根で夏期を乗り越えているのです。このサイクルで一部の昆虫も合わせています。
秋に花を付ける草花は、冬が嫌いなために冬期を種や球根で乗り越えているのです。
気温が1~3度上昇することで生物の20~30%が絶滅の危機に瀕する、と言われています。地球温暖化により高温の夏期が長期化することから、春に咲く草花、秋に咲く草花、昆虫それぞれが淘汰されていくのでしょう。
はじめ人間ギャートルズのお金
以前来園されたお客様から「なぜ、ここにギャートルズのお金があるのですか」と尋ねられたことがありました。
はじめ人間ギャートルズは、私が小さい頃見ていたアニメ番組で、原始時代に主人公のはじめ人間ゴンが相棒のドテチンやゴンの家族とともにマンモス狩りをするストーリーでした。この中で大きな石のお金が出てきます。おそらくこのお金でマンモスの肉と交換していたのでしょう。
当園にある石のオブジェはギャートルズのお金ではありません。もし、お金として流通するのなら小判くらいの価値があるのではないかと思っています。
このオブジェの大きさが分かるように私の愛車の「ネコ」を並べてみました。「ネコ」は動物ではありません。手押し一輪車のことです。
まさしく「ネコに小判」です。
栄養豊富な雑草
畑で嫌われる雑草のひとつにスベリヒユがあります。スベリヒユは多肉植物のような葉っぱでポーチュラカに似たかわいい花を咲かせますが、抜いても抜いても生えてくるのでため息が出ます。
このスベリヒユは食べられることを知っていますか。しかも栄養価が高いスーパーフードなのです。スベリヒユは世界中で食べられフランス料理にも使われたり、沖縄や東北地方では昔から食べられていたみたいです。
スベリヒユの葉っぱはサラダでも食べられモロヘイヤとレタスを一緒に食べた食感がありますが、シュウ酸が多く含まれており結石を作る原因になりますので生ではお勧めできません。
お勧めはスベリヒユのおひたしです。お湯を沸かしひとつまみの塩とスベリヒユを1分間茹でて、流水でアク抜きして、刻んでゴマ油、砂糖、しょう油を適量加えてあえるだけです。
また、カラカラに干すと保存食として重宝します。
夏の水やり
今日は二十四節季の処暑、暑さが和らぐ頃とされますが、まだまだ猛暑日の毎日です。
熱中症を防ぐためにも水分補給は必須で、これは植物も同じです。
植物は肥料が足らなくても枯れることはありませんが、水分が足らないと枯れてしまいます。そのために何げなく水やりをしていますが、実は「水やり三年」と言われるくらい水やりは難しいのです。
植物は水分を根っこの先端から吸収し、導管を通じて末端の葉っぱまで浸透圧で吸い上げられます。運ばれた水分は葉緑体によりCO2と光エネルギーから有機物が作られたり、暑い温度を下げるために蒸散に使われます。このことが正しく理解されないと水やりのタイミングと水の量を判断できません。これらは経験から分かってきます。
私は地植えする植物には植える時以外は基本的に水やりしません。
問題なのが鉢植えの植物の水やりです。この時期は朝夕の2回の水やりが必要と言われますが、土が乾いていないのに水やりを続けると根腐れをおこして弱ったり枯れてしまいます。一日一回の水やりで十分で、朝と夕方どちらがいいかと尋ねられますが、光合成に水を使うので植物が光合成をし始める朝が良いという説が多いですが、私はハングリー精神を養うためにも夕方水やりしています。
一日一回の水やりが困難な方は、自動灌水機もありますが、鉢の大きさを一サイズ大きくしておくとか、西日のあたらない場所に鉢を置くとか、陶器製も鉢をプラスチック鉢に変える等の工夫が大事です。
ツユクサの不思議
真夏に青い花を咲かせるツユクサは、早朝から咲きだし昼にはしぼむことから朝露のように儚い様子から名付けられたそうです。
しかし儚いイメージのツユクサですが、繁殖力の強い植物で茎の節目から根を出しどんどん横に広がっていきます。伐根除草しても除草したツユクサを他の場所に捨てると、そこから根付き広がっていきます。以前わが家でも白い花をつけるトキワツユクサが自然に育ち、そのままにしていたら他の地被類を駆逐してあっという間に広がったことがありました。
ツユクサの花は毎日同じ花がずっと咲いているように見えますが、実は1日花で毎日別の花を咲かせています。ツユクサの花びらをよく見ると、上に向いて咲く青色の花びら2枚と、下に向いて咲く白い花びら1枚の計3枚です。
ツユクサのおしべは不思議で、花の上から3本、真ん中が1本、下が2本の計6本の3種類のおしべがあり、花粉をつけるのは下の2本のおしべだけです。ツユクサは蜜を作りませんが、その鮮やかな青色で昆虫を呼び寄せます。
ツユクサの受粉はさらに不思議で、受粉は花が開くときはおしべとめしべが接触して自家受粉(アサガオの受粉と同じ)、花が開いているときは昆虫を利用した他家受粉、花がしぼむときはおしべとめしべが接触して自家受粉するという、自家受粉と他家受粉のメリット・デメリットを知りつくしたとしか思えません。