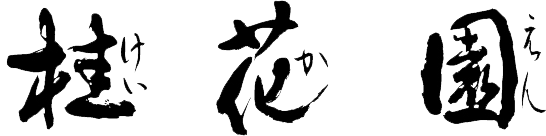指宿スカイラインの川辺ICと知覧IC間の下り車線を走ると、我らが長渕剛兄貴の名曲「乾杯」のサビの部分が聞こえます。これは道路に溝がいくつも掘ってあり、タイヤが接触すると音が出る仕組みで、想像するよりはっきり大きく聞こえます。
10月1日より指宿スカイラインは通行料の改定があり、谷山IC~頴娃IC間は全区間走行しても大型車を含め100円になりました。
ちなみに、当区間は自転車も走行できますし、入口料金所が谷山ICで桂花園経由の出口料金所が谷山ICの場合も100円になります。
これから紅葉が見ごろになります。鹿児島市内から某そうめん流しに行く際は、指宿スカイラインを利用して、一瞬ですが「乾杯」を聞いてみてください。自慢になりますよ。